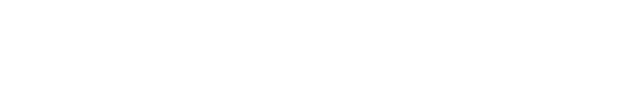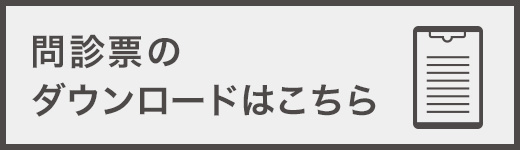吐き気・嘔吐
・吐き気がする
・食べ物をもどしてしまった
・胃の不快感やむかむかする感じが続いている
・食欲がない
これらの症状のように、吐き気・嘔吐により不快感をかんじることがあります。
一時的な体調不良から、深刻な病気のサインである場合まで、さまざまな原因が考えられます。
考えられる病気
悪心や嘔吐は消化器疾患だけでなく、身体のさまざまな臓器に共通する症状です。
原因によって治療法が異なるため、長引く場合には詳細な検査が必要になることもあります。
消化器内科の病気
感染性胃腸炎
病原性をもつウイルスや細菌に感染することで発症し、多くが下痢をともないます。
主に細菌性とウイルス性に大別されますが、多くの原因がウイルス性です。
ウイルス性腸炎の原因として有名なものは、ノロウイルスです。
ノロウイルスは冬季に流行しやすいウイルスです。
ノロウイルスに感染した患者の糞便や吐物を触ることで感染したり、家庭や共同施設での飛沫感染、あるいはノロウイルスに汚染された二枚貝(牡蠣など)を食べることで感染します。
そのほか、ロタウイルス、腸管アデノウイルスなど多岐にわたります。
細菌性腸炎は、ウイルス性腸炎より症状が重くなる傾向にあります。
ときに高熱がつづき、血便が出ることもあります。
多くが細菌に汚染された食品を食べることで感染しますが、汚染された便や吐物を触ることで感染することもあります。
鶏肉が原因となるカンピロバクター、卵が原因となるサルモネラ、牛や豚が原因となる腸管出血性大腸菌、魚介が原因となる腸炎ビブリオ、おにぎりやサンドイッチなど人の手を介して感染する黄色ブドウ球菌などが代表的です。
ウイルス性胃腸炎の場合には保存的治療(脱水の補正、症状に対する対症療法)が中心です。
細菌性腸炎をうたがう場合には抗生物質による治療を考慮することもあります。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、いずれも胃や十二指腸腸の壁が傷ついて炎症や痛みを引き起こす病気です。
胃酸や消化酵素の影響によって防御因子と攻撃因子のバランスが崩れ、粘膜が傷ついて欠損が生じる状態のことを指します。
主な原因は、ピロリ菌の感染や鎮痛剤の長期使用、ストレス、喫煙、飲酒などが挙げられます。
よくある症状は、軽いものであるとみぞおち周辺の痛みや胸焼け、吐き気、食欲不振などです。
潰瘍からの出血が大量だった場合、墨のような真っ黒なものを嘔吐したり、真っ黒な便が出ることもあります。
また、放置すると粘膜の深部まで損傷が進行し、穿孔(消化管に穴が開く状態)といった合併症を引き起こすことがあります。
多くが内視鏡により診断され、胃薬による治療やピロリ菌の治療がなされます。
潰瘍からの出血が止まらない場合には、内視鏡的止血術が行われることもあります。
逆流性食道炎
逆流性食道炎は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流し、食道の粘膜が炎症を起こす病気です。
通常、胃と食道の間にある筋肉(下部食道括約筋)が逆流を防いでいますが、この機能が低下することで胃酸が食道へ逆流しやすくなります。
結果、胃酸が原因で食道の炎症をひきおこし、逆流性食道炎にかかりやすくなります。
よくある症状には、胸焼け、胃酸の逆流感、喉の違和感、慢性的な咳、声がれなどがあります。
原因としては、肥満、過食、脂っこい食事、アルコールや喫煙、ストレス、食後すぐに横になる習慣などが挙げられます。
また、妊娠や加齢による筋肉の緩みも要因になります。
症状を放置すると食道潰瘍やバレット食道といった重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、生活習慣の改善や薬物治療が重要です。
腸閉塞
腸閉塞は、腸の内容物が正常に流れなくなる状態で、腸管の物理的な閉塞や腸の動きの低下が原因で起こります。
腸が詰まることで、消化物やガスが滞り、重篤な症状を引き起こします。
腸閉塞は機械的腸閉塞と麻痺性腸閉塞に分類されます。
機械的腸閉塞とは、腸管内の腫瘍・異物・術後の癒着・捻転(ねじれること)・ヘルニアなどによって腸管が物理的に閉塞することでおこります。
とくに機械的腸閉塞のなかでも血流障害をともなう絞扼性腸閉塞になると、放置すると腸管壊死や穿孔をひきおこし重篤化するので、緊急手術などの対応が必要です。
麻痺性腸閉塞とは、手術後・腹腔内の感染症・薬剤などの影響え腸の蠕動運動が低下し、内容物が流れなくなることを指します。
いずれの腸閉塞も、よくある症状としては腹痛・腹部膨満・吐き気や嘔吐・排便や排ガス(おなら)の停止などがあります。
原因は、術後の癒着やヘルニア、腸管内の腫瘍、腸重積、炎症性腸疾患など多岐にわたります。
また、腸の動きが低下する麻痺性腸閉塞は、手術後や感染症、電解質異常が原因となることがあります。
放置すると腸管壊死や穿孔を引き起こす危険があるため、早期の診断と治療が必要です。
急性肝炎
急性肝炎は、ウイルスやアルコール、薬剤などが原因で肝臓に炎症が起こる病気です。
肝炎ウイルス(A型肝炎ウイルス・B型肝炎ウイルス・EBウイルスなど)が最も一般的な原因で、飲食物や血液、体液を通じて感染します。
ほかアルコールの過剰摂取や薬剤の副作用でも発症します。
肝臓の細胞が直接攻撃されたり、体の免疫反応が過剰になることで肝細胞が傷つき、炎症をひきおこすことが肝炎の発症機序としてあげられています。
症状としては、倦怠感、発熱、食欲不振、黄疸(皮膚や目が黄色くなる)、尿の色が濃くなる、吐き気や嘔吐などがあります。
最初は顕著な症状が出ずに、インフルエンザや胃腸炎などと思われることもあります。
多くは一時的に治癒しますが、重症化すると肝不全に進行することもあります。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシア(FD)は、胃や消化管に明らかな異常がないのに、胃の不快な症状が続く病気です。
発症の機序としては、胃の動きの異常、胃の過敏性、ストレスや自律神経の乱れなどが関与しています。
原因は明確ではありませんが、ストレス、食生活の乱れ、ピロリ菌感染、胃酸分泌の異常などが関係すると考えられています。
よくある症状には、食後の胃のもたれ、早い段階で満腹感を感じる、胃の痛みや灼熱感、吐き気などがあります。
これらの症状が生活の質を低下させることがありますが、胃カメラなどの検査では異常が見つからないのが特徴です。
治療には、食事や生活習慣の改善、薬物療法、ストレス管理が用いられます。
消化器内科以外の病気
腎不全
腎臓は尿をつくりだす臓器として知られています。
人間は腎臓から体内の老廃物を濾しだし、尿として排泄することで体内を正常化しています。
腎不全は、腎臓が正常に働かなくなり、体内の老廃物や余分な水分を排出できなくなる状態です。
原因としては、糖尿病や高血圧といった慢性疾患、腎臓の病気(糸球体腎炎など)、脱水や血液循環の問題(心不全やショックなど)などさまざまな疾患が挙げられます。
急性腎不全は短期間で機能が低下し、慢性腎不全は徐々に進行します。
よくある症状には、むくみ、倦怠感、息切れ、尿量の減少、皮膚のかゆみ、吐き気などがあります。
診断には、血液検査でクレアチニンや尿素窒素を測定し、腎臓の機能を評価します。
また、尿検査や画像検査(エコーやCT)も原因を調べるために行われます。
糖尿病性ケトアシドーシス
糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)は、糖尿病(特に1型)でインスリンが不足したときに起こる危険な状態です。
(2型糖尿病の方でも、スポーツドリンクなどの糖分の入った飲料を大量に接種したときに起こすことがあります。)
インスリンの量が血糖値にくらべ大幅に不足すると、体はエネルギー源として脂肪を分解し、ケトン体という酸性物質が過剰に作られます。
これにより血液が酸性になる(アシドーシス)ことで症状が現れます。
原因としては、インスリン注射の不足、感染症、ストレス、けが、大量の糖分摂取などが挙げられます。
よくある症状には、喉の渇き、頻尿、吐き気、腹痛、疲労、息がフルーツのようなにおいになるなどが挙げられ、重症化すると意識障害などがあります。
診断は、血液検査で高血糖、血中のケトン体増加、酸性度を確認します。
放置すると命に関わるため、早急な治療が必要です。
低血糖症状
低血糖は、血液中の糖分(グルコース)が異常に低くなる状態です。
体や脳が十分なエネルギーを得られなくなるため、さまざまな症状をひきおこします。
原因としては、糖尿病の治療薬(インスリンや血糖降下薬)の過剰投与、食事の不足、激しい運動、飲酒などがあり、まれなものではインスリン産生腫瘍(インスリノーマ)・副腎不全・肝硬変や急性肝不全・腎不全もあります。
機序としては、血糖値を維持するホルモンの働きが追いつかず、体が必要なエネルギーを供給できなくなることで症状が現れます。
よくある症状には、冷や汗、動悸、ふるえ、空腹感、頭痛、めまい、意識障害、最悪の場合はけいれんや昏睡があります。
診断は、血糖値が70mg/dL以下であることを確認することと、症状が一致することで行います。
症状があればすぐに糖分を補給し、改善しない場合は医療機関を受診することが大切です。
高カルシウム血症
高カルシウム血症は、血液中のカルシウム濃度が異常に高くなる状態で、体にさまざまな影響を与えます。
カルシウムは体内で重要な役割を果たしますが、過剰になると神経や筋肉の働きが乱れます。
嘔吐はその一つの症状です。カルシウムが高すぎると、胃腸の動きが鈍くなり、吐き気や嘔吐が引き起こされます。
原因としては、副甲状腺機能亢進症(副甲状腺からのホルモン過剰分泌)、がん(特に骨転移)、腎不全、ビタミンD過剰などがあります。
よくある症状には、吐き気、嘔吐、便秘、脱力感、食欲不振、意識障害、脱水症状などがあります。
診断は血液検査でカルシウム濃度を測定し、必要に応じて副甲状腺ホルモンやビタミンDの検査を行います。
甲状腺機能亢進症
甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)は、首の全面にある甲状腺から過剰に甲状腺ホルモンが分泌される状態です。
甲状腺ホルモンは体全体のエネルギー消費を調整しており、身体の代謝をうながすホルモンであり、この分泌が過剰になることで体の代謝が異常に速くなり、さまざまな症状が現れます。
原因としては、自己免疫疾患であるバセドウ病が最も一般的です。
免疫システムが誤って甲状腺を刺激することにより、ホルモンが過剰に分泌されます。また、甲状腺炎や腫瘍も原因となることがあります。
よくある症状には、体重減少、動悸、発汗、手のふるえ、眠れない、イライラ感、疲れやすさなどがあります。
また、バセドウ病の場合は目が突出することもあります。
診断は血液検査で甲状腺ホルモン(T3、T4)や、甲状腺刺激ホルモン(TSH)の異常を確認し、超音波やスキャンで甲状腺の状態を調べます。
治療には薬物療法、放射線治療、手術などが行われます。
片頭痛
片頭痛は、頭に激しい痛みが生じる頭痛の一種です。
片頭痛の機序は未だに十分に解明されていませんが、脳の血管が拡張し、周囲の三叉神経を刺激することが関係しているのではないかといわれています。。
片頭痛の原因は、遺伝や環境要因、ストレス、ホルモンの変動(特に女性)、食べ物や飲み物、睡眠不足などが影響します。
よくある症状には、片側の強い拍動性の頭痛、吐き気、嘔吐、音や光に対する過敏症があります。
また、頭痛が始まる前に視覚的な異常(光の点が見えるなど)が現れることもあります(前兆)。
片頭痛は数時間から数日続くことがあり、日常生活に大きな影響を与えることがあります。
診断は、症状や病歴を基に医師が行います。必要に応じて、他の疾患を排除するためにCTスキャンやMRIが使用されることもあります。
治療には、痛みを和らげる薬や予防薬が使われ、生活習慣の改善も重要です。
脳腫瘍・脳卒中
脳腫瘍や脳卒中による悪心(吐き気)や嘔吐は、脳の圧力が上昇することが原因で起こります。
脳は非常に敏感な臓器で、腫瘍や脳卒中(脳梗塞や脳出血)が発生すると、脳内の圧力(頭蓋内圧)が高まり、これが嘔吐中枢を刺激します。これにより、吐き気や嘔吐が引き起こされます。
脳腫瘍は腫瘍が大きくなることで脳の他の部分を圧迫し、脳卒中は血流の遮断により脳細胞が損傷を受け、これが頭蓋内圧を増加させます。
よくある症状には、持続的な頭痛、吐き気、嘔吐、意識障害(ぼんやりとした状態や混乱)、麻痺や言語障害などがあります。
診断は、CTスキャンやMRIを用いて脳の画像を確認することで行います。
これにより、脳腫瘍や脳卒中の有無が確認され、適切な治療が進められます。
妊娠悪阻(つわり)
わり(妊娠悪阻)は、妊娠初期に見られる吐き気や嘔吐の症状で、通常は妊娠6週から12週の間に発症します。
妊娠によって分泌されるホルモン(特にhCGやエストロゲン)が消化器系に影響を与えるため、胃腸の働きが乱れ、吐き気や嘔吐が起こると言われていますが、詳しい機序はいまだわかっていないこともあります。
原因としては、ホルモンの急激な変動、ストレス、疲労、空腹などが関与すると考えられています。
特に、hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)は妊娠初期に急増し、つわりの症状を引き起こすことが知られています。
朝起きたときや食事の前に感じる吐き気、嘔吐、匂いに敏感になること、食欲不振などです。ほとんどの場合、軽度のつわりは自然に改善しますが、重度の症状(妊娠悪阻)では、食事が取れず脱水や栄養不足になることがあり、治療が必要です。
妊娠中にできない検査や、処方できない薬もありますので、かならず妊娠の可能性がある場合はお申し出ください。
診断への検査方法
症状の聴取を行いつつ、可能性の高い疾患を区別するために検査をおこないます。
消化器の疾患をうたがう場合には便培養や内視鏡検査をおすすめしますが、診察から消化器疾患以外の疾患を疑うようであれば、優先的に血液検査などをおこないます。
血液検査
肝機能、腎機能、甲状腺機能、カルシウムをふくめた電解質、血糖値を検査することが可能です。
上にあげたような消化器以外の疾患を鑑別する際に重要になります。
細菌培養検査
細菌性腸炎を疑った場合に行います。
便中の病原性細菌を確認する目的で行います。
便を採取し検査に提出する方法が一般的です。
内視鏡検査
胃潰瘍や十二指腸潰瘍、逆流性食道炎を疑った場合には、内視鏡検査で診断をつけることが一般的です。
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ検査)で多くは診断をつけることができます。
活動性出血を認める場合は、その場で内視鏡的止血術をする場合があります。
画像診断
頭痛を伴う吐き気・嘔吐の場合には、頭部CT撮影およびMRI撮影で頭蓋内の病気がないか確認をします。
また、腸閉塞をうたがう場合にはお腹のレントゲン撮影でガスの異常の有無を確認し、必要であれば腹部CT検査にすすむことがあります。
自宅でできる対処法
悪心・嘔吐が一時的なものである場合、自宅でできる対処法を試してみることも有効です。
ただし、症状が続く場合や重篤な症状が見られる場合は、医療機関の受診が必要です。
食事と水分補給
- 脱水を防ぐ: 水分を少量ずつ頻回に摂取します。スポーツドリンクなども有効です。
- 消化に良い食事: おかゆやスープ、クラッカーなど胃に負担の少ないものを選びましょう。
環境の整備
- 安静を保つ: 体を横にしてリラックスできる環境を整えます。
- 空気を入れ替える: 新鮮な空気を取り込むことで気分が良くなる場合があります。
市販薬の使用
- 胃薬や制吐薬を使用する場合は、薬剤師や医師に相談してください。
当クリニックでできること
当クリニックでは、悪心・嘔吐の原因究明と治療を専門的に行っています。
以下のような対応が可能です。
- 詳しい問診と診察:患者さん一人ひとりに寄り添い、丁寧に症状を伺います。
- 最新の内視鏡機器:痛みを最小限に抑えた胃カメラ検査を提供しています。
- 迅速な検査結果:内視鏡検査の結果をその場でお伝えします。
- 治療プランの提案:原因に応じて、薬物療法や生活改善の指導を行います。
- 病診連携:消化器内科以外の疾患をうたがう場合には、適切な医療機関へご紹介いたします。
悪心や嘔吐は、日常的な体調不良から重大な疾患のサインまで、さまざまな原因で起こる症状です。
一時的に改善しても、原因を正確に診断し、適切に治療することが重要です。
もし症状でお悩みの場合は、ぜひ当クリニックにご相談ください。
一人ひとりに寄り添った治療を提供いたします。