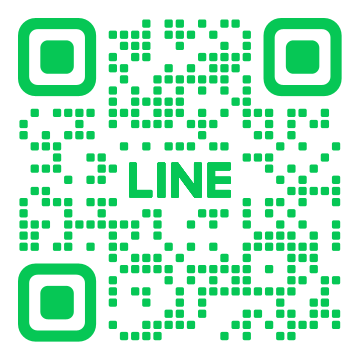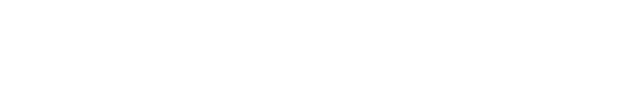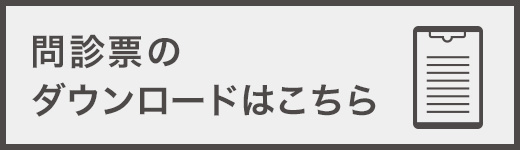大腸ポリープ切除後の食事の注意点やおすすめの食事メニュー
大腸ポリープ切除後の食事と生活制限はなぜ必要?
大腸ポリープは、内視鏡で「切って、取れば終わり」というイメージをお持ちの方が多いのですが、実はポリープを切除したあとの大腸粘膜には小さな“傷跡”が残ります。この傷跡は、ちょうどかさぶたが出来る前の皮膚のようにとても繊細で、わずかな刺激でも出血や炎症を起こしやすい状態です。
そこで大切になるのが、胃腸に負担をかけない食事と腸内圧を上げない生活です。脂っこい料理やアルコール、食物繊維が多くて消化に時間がかかる食品は、腸の動きを活発にして出血リスクを高めます。また、激しい運動や長時間の入浴・サウナは血流を一気に増やし、同じく出血を招く恐れがあります。
切除翌日以降は「もう痛みもないし普段通りで大丈夫」と思いがちですが、粘膜が完全に再生し、傷が塞がるまでには少なくとも1週間前後かかります。
この期間を安全に過ごすかどうかで、再診の有無やその後の腸の健康状態が大きく変わります。
当院では、術後の出血や腹痛を防ぐために、食事と生活の具体的な注意点を丁寧にお伝えし、必要に応じて電話でのご相談も受け付けています。
「たった1週間、されど1週間」。
適切なケアを行うことで、再発予防と快適な日常への早期復帰がぐっと近づきます。まずは基本的な考え方として、「腸を休ませること」が大切だと覚えておきましょう。
大腸ポリープ切除当日の食事メニューと生活制限について
食事:油分・繊維質を避けた軟らかい食事を
切除当日は、基本的に野菜やきのこ、海藻などの食物繊維や避けた軟らかい食事にしてください。油の少ないスープやおかゆ、やわらかいうどんや卵料理などが好ましいです。
とはいえ、体内の水分が不足すると血液が濃くなり、血栓や便秘を招きやすくなります。脱水を防ぐために、常温の水・白湯・薄めたスポーツドリンク・経口補水液など、刺激の少ない透明な飲み物をコップ1杯ずつ、こまめに摂取しましょう。冷たい飲料や炭酸、カフェインを含む飲み物は腸を刺激しやすいため避けてください。
生活制限:安静第一、血流を上げないこと
入浴はシャワーのみに限定
長時間の湯船やサウナは体温と血流を急激に上げるため、出血リスクが高まります。ぬるめのシャワーで短時間(目安5分以内)にとどめ、患部を温め過ぎないよう注意しましょう。
- 運動・力仕事は禁止
重い荷物を持ち上げたり、階段を駆け上がるなどの負荷は、腹圧を高めて出血の原因になります。最低でも当日は終日安静、デスクワークも含めた長時間の座位は控え、ソファやベッドで横になって休むことをおすすめします。
- 飲酒、喫煙は厳禁
アルコールは血管を拡張させ出血を助長し、喫煙は血流を悪化させ傷の治りを遅らせます。どうしても我慢できない方でも、術後1週間は禁酒・禁煙を徹底してください。
- 車の運転は控える
低血糖や脱水でふらつきを感じる場合があり、事故の危険性が高まります。術後に麻酔を使用した場合は眠気が残ることもあるため、少なくとも当日は運転を避け、公共交通機関やご家族の送迎を利用してください。
当日の過ごし方のポイント
- 冷た過ぎず熱過ぎない水分をこまめに補給
- トイレはいきまないよう深呼吸してゆっくり
- 眠気やだるさがある場合は無理せず横になる
- お腹に痛みや強い張りを感じたら、早めに当院へ連絡
切除当日は、「腸を極力動かさず、血流と腹圧を上げないこと」が鉄則です。この24時間を大切に過ごすことで、翌日以降の回復スピードが格段に変わります。
大腸ポリープ切除後、1週間の食事と生活制限について
切除翌日から1週間は、**「回復期のリハビリ期間」**と考えてください。
見た目は普通の便が出ても、粘膜はまだ薄い皮膜で覆われただけの“新生組織”です。
ここで無理をすると、出血や穿孔(穴あき)のリスクが高まります。そこで、日ごとに段階を踏んで食事と生活を戻すことがポイントです。
<おすすめの食事の目安>
|
術後日数 |
食事のかたさ |
主なメニュー例 |
注意点 |
|
1〜2日目 |
流動食〜全粥 |
重湯 具なし味噌汁 ポタージュスープ |
冷まし気味にしてゆっくり飲む |
|
3〜4日目 |
軟菜食 |
7分粥 豆腐ハンバーグ 白身魚の蒸し煮 |
炒め物・揚げ物はNG |
|
5〜7日目 |
普通食に近い軟食 |
全粥〜軟飯 柔らかい鶏ささみ 温野菜 |
ゴボウ・キノコなど不溶性繊維は避ける |
コツ① 低脂肪・高たんぱくを意識
豆腐・卵・白身魚・鶏むね肉など、消化が良く粘膜再生に必要なたんぱく質をしっかり摂りましょう。脂質は腸蠕動を強めるため控えめに。
コツ② よく噛んで少量ずつ
一口30回を目安に咀嚼し、1日3食を4〜5回の少量分割食に変えると、腸の負担をさらに軽減できます。
コツ③ 水溶性食物繊維を上手に活用
リンゴのすりおろしやバナナ、にんじんスープなどの水溶性食物繊維は、便を柔らかくし傷口を刺激しません。整腸作用も期待でき、便秘気味の方におすすめです。
<生活制限のステップ>
|
項目 |
術後1〜2日目 |
術後3〜7日目 |
注意点・補足 |
|
運動 |
室内での軽い歩行のみ |
ゆっくりした散歩(30分以内) |
ジョギング・筋トレはまだ禁止 |
|
入浴 |
シャワーのみ(短時間) |
37〜38℃のぬるめ湯に5〜10分 |
長湯・サウナ・温泉はNG |
|
仕事復帰 |
原則自宅療養 |
デスクワークなら再開可 |
立ち仕事・力仕事は医師の許可が出るまで控える |
食事制限が必要な期間とは
「いつから普通の食事に戻していいの?」というご質問を多くいただきますが、少なくとも術後3日目以降、可能なら術後1週間以降です。
Evoto
ただしこれは“標準的な大きさ(およそ5〜10mm未満)のポリープ”を切除した場合。ポリープが大きい、複数を同時に切除した、抗血栓薬を内服しているといったケースでは、10日〜2週間ほど慎重に過ごしていただくことがあります。
期間を判断する3つのポイント
切除部位の大きさと深さ
大型ポリープや茎が太いタイプは、傷が深くなるため再生に時間がかかります。医師が「大きめでした」と説明した場合は、必ず期間延長を意識しましょう。
出血・痛み・発熱などの症状
術後3〜4日目までに鮮血便や腹痛が起きた場合は、粘膜の治癒が遅れているサイン。いったん全粥などの軟食に戻し、症状が落ち着くまでは無理に普通食へ移行しないことが大切です。
基礎疾患やお薬の影響
抗血小板薬・抗凝固薬を服用している方、糖尿病や慢性腎臓病などで血流や免疫が低下している方は、傷の治りが遅い傾向にあります。主治医と連携しながら、食事レベルを慎重に段階アップしていきましょう。
<食事制限期間の一覧表>
|
食事制限期間の目安 |
ポリープ・患者の条件 |
主な理由・注意点 |
|
約1週間 |
標準的な大きさ(5〜10 mm 未満)を1個切除 |
粘膜の再生が通常速度で進むため。術後3日目までの症状が安定していれば、7日目以降に柔らかめの普通食へ移行可。 |
|
10〜14日 |
大型ポリープ(10 mm 以上)または茎が太いタイプ |
傷が深く再生に時間がかかる。出血・穿孔リスクを下げるため、軟菜食を長めに継続。 |
|
10〜14日 |
複数ポリープを同時切除 |
切除部位が多数あるため、腸管全体の炎症・出血リスクが高い。経過観察中に少量ずつ食事レベルを上げる。 |
|
10日〜2週間以上も(医師の判断) |
抗血栓薬内服中・糖尿病・慢性腎臓病など基礎疾患あり |
血流や免疫機能の影響で治癒が遅れる傾向。主治医と連携し、症状や検査結果を見ながら段階的に解除。 |
※個人差はありますのでおおよその目安となります。
大腸ポリープ切除後の食事と生活制限でよくある質問
Q.乳製品はいつから大丈夫?
A.牛乳・ヨーグルト・チーズなどの乳製品は、脂質と乳糖が腸を刺激しやすい食品です。少量であれば術後3〜5日目から試せますが、まずはプレーンヨーグルト大さじ1杯程度から始め、腹痛や下痢がないか確認しましょう。チーズやバターなど高脂肪のものは、1週間〜10日ほど経ってからが安心です。
Q.コーヒーやお茶はOK?
A.カフェインは腸管の蠕動を促す作用があり、出血リスクをわずかに高めます。術後3日目までは控え、4日目以降に薄めたものを少量から再開してください。冷たいアイスコーヒーより、常温またはホットで飲むほうが刺激が少なくおすすめです。
Q.アルコールは1週間禁酒?
A.はい。アルコールは血管拡張と血流増加作用により、術後出血の最大リスク要因です。当院でも再出血で救急搬送となった方の多くが、早期の飲酒再開が原因でした。安全のため最低1週間、できれば10日間の禁酒を厳守しましょう。
Q.便秘になったらどうすれば?
A.いきみは腹圧を上げ、傷口に強い負担がかかります。
便秘を感じたら、
- 水溶性食物繊維を含むバナナ・リンゴ煮・オートミール粥を追加
- 水分を1日5〜2L目安にこまめに補給
Q.体力作りでウォーキングは?
A.歩行は回復を促す適度な運動ですが、最初の3日間は室内歩行にとどめるのが基本です。4日目以降は1回30分以内、ゆっくりしたペースで平坦な道を歩いてください。階段ダッシュや坂道ウォーキング、スピードウォークは1週間過ぎてからにしましょう。
Q.旅行や出張は入れていい?
A.術後1週間以内の長距離移動はおすすめしません。長時間同じ姿勢が続くと腹圧が高まり、また食事コントロールも難しくなります。
どうしても外出が必要な場合は、
- 移動は2時間ごとに休憩を挟む
- 食事はコンビニのお粥ややわらかいサンドイッチなど低脂肪・低食物繊維を選択
- アルコールはもちろんNG
「ちょっと相談してみたいな」「もう少し詳しい説明を聞きたい」というお気持ちになられたら、どうぞ遠慮なく当院へお問い合わせください。
お電話などから、検査や予約に関するご質問をお受けしています。
もちろん、事前のカウンセリングだけでも構いません。スタッフ一同、皆さまの健康を最優先に考え、誠心誠意サポートさせていただきます。
「当クリニックのご予約はLINE予約がおすすめです!」