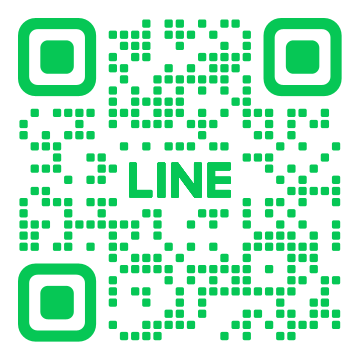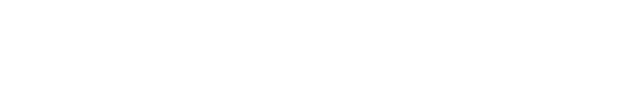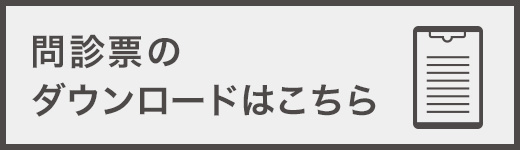30代も注意!脂質異常症・高脂血症の違いとコレステロール値を下げる5つのコツ
はじめに
「最近、健康診断で“コレステロール値が高め”と言われてしまった…」——そんなお声を多く耳にします。特に30代前後は、仕事や家庭で忙しく、自分の健康を後回しにしがちな時期。しかし、この年代こそ“脂質異常症”を放置しないことが大切です。
脂質異常症とは、血液中のLDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL(善玉)コレステロールが低い状態を指します。自覚症状がほとんどないため、知らないうちに動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる疾患のリスクが高まります。
本記事では、脂質異常症と高脂血症の違いを整理しながら、コレステロールを無理なく下げる5つのコツをわかりやすく解説します。
30代からでも脂質異常に要注意?
「脂質異常症なんて中高年の病気でしょう?」と思われがちですが、実は30代前後から数値が悪化しやすいことが知られています。※
若い頃は基礎代謝が高く多少の暴飲暴食でも大きな影響は出にくいのですが、30代半ばを過ぎると代謝は緩やかに低下。さらに忙しさから運動不足や夜遅い食事、アルコール量の増加など生活習慣が乱れやすく、気づかぬうちに内臓脂肪が増えていきます。
また、仕事のストレスや睡眠不足はホルモンバランスを乱し、中性脂肪やLDLコレステロールを上げる一因に。さらに男性は40代、女性は閉経後に悪玉コレステロールが急上昇しやすいと言われるため、「今は大丈夫」と放置していると、数年後に一気にリスクが高まる可能性があります。
最近の研究では、20〜30代で脂質代謝が乱れたまま放置すると、40代以降に動脈硬化が進行しやすいことも示唆されています。つまり、30代は“予防”と“改善”の分岐点。早めに数値を把握し、生活を立て直すことが、将来の心筋梗塞や脳卒中の予防につながります。当クリニックでも「まだ若いから」と思っていた方が、健診結果をきっかけに受診されるケースが増えています。
自覚症状がないうちに対策を始める——それが健康長寿への近道です。
※厚生労働省:令和5年「国民健康・栄養調査」の結果
(2023年〈国民健康・栄養調査〉の年齢階級別データで、総コレステロール平均値が20–29歳より30–39歳で明確に上昇。男性139 mg/dL→約150 mg/dL、女性143 mg/dL→150 mg/dL台へ。)
脂質異常症の5つの危険性
脂質異常症は“静かに進む病気”です。血中脂質のバランスが崩れると、気づかないうちに動脈硬化が進行し、やがて心筋梗塞・脳卒中など突然死につながる重篤な病気を引き起こします。
世界保健機関(WHO)は、心血管疾患が世界で年間1,790万人の死因となり、その85%が心筋梗塞と脳卒中であると報告しています。さらに、高コレステロール自体が年間約260万件の死亡に関与しているとも示されています。
こうした背景から、日本動脈硬化学会の最新ガイドラインでも、脂質異常症の早期発見と管理が一次予防の中心課題と明記されています。
悪玉コレステロール(LDL‐C)が血管を詰まらせる
LDL‐C は“血管のサビ”とも呼ばれ、数値が高いほど冠動脈イベント(心筋梗塞など)が直線的に増えることが国内外の大規模研究で証明されています。
スタチン治療などで LDL‐C を 1 mmol/L(約39 mg/dL)下げると、主要心血管イベントを 20%以上減らせるというメタ解析結果も報告されています。
善玉コレステロール(HDL‐C)が低いと修復機能が働かない
HDL‐C は余分なコレステロールを回収して肝臓に戻す“血管の掃除屋”ですが、40 mg/dL 未満になると動脈硬化予防効果が弱まり、心疾患リスクが高まると解説されています。
中性脂肪(トリグリセリド)の上昇は二重の脅威
高トリグリセリド血症(150 mg/dL 以上)は動脈硬化を促進し、冠動脈疾患や脳梗塞の発症率を押し上げる要因になります。
さらに 1,000 mg/dL 以上になると急性膵炎を誘発しやすく、重症化すると命に関わることが症例報告から分かっています。
脂質異常症は“サイレントキラー”
症状が出にくいため「健康診断の数値が唯一の警告サイン」とも言われ、放置すれば突然の心筋梗塞・脳梗塞につながります。
厚生労働省 e-ヘルスネットも、脂質異常症は動脈硬化の主要危険因子であり、管理を怠ると脳梗塞・心筋梗塞を招くと警告しています。
心臓・脳だけでなく全身に影響
動脈が狭く硬くなると、足の血流障害(閉塞性動脈硬化症)や腎機能低下など多臓器に波及します。
アメリカ心臓協会(AHA)は「高コレステロールは心臓発作・脳卒中リスクを増やすため、20 歳以上は 4〜6 年ごとに脂質チェックが必要」と推奨しています。
早期発見と継続管理が命を守る
脂質異常症は年齢とともにリスクが加速しますが、きちんと数値を把握し、食事・運動・薬物療法を組み合わせることで十分コントロールが可能です。動脈硬化が進行してからでは取り返しがつきません。次の健診結果を待たず、まずは一度、血液検査と医師の評価を受けてみましょう。
脂質異常症と高血圧症の5つの違い
「何を測る病気?」——診断基準の比較
脂質異常症は、血液中の脂質バランスが崩れた状態です。日本動脈硬化学会Q&Aでは「LDLコレステロール140 mg/dL以上」「HDLコレステロール40 mg/dL未満」「中性脂肪150 mg/dL以上」のいずれかを満たすと診断すると示されています。
高血圧症は血圧そのものの異常で、日本高血圧学会の一般向け資料では「診察室血圧140/90 mmHg以上」が基準と明記されています。
つまり、脂質異常症は**“コレステロールや中性脂肪の数値”、高血圧症は“血液を押し出す圧力”**をそれぞれチェックする病気です。
血管へのダメージは“質”と“圧”の違い
脂質異常症では余分なLDLが血管壁に沈着し、「コレステロールのサビ」がプラークをつくります。
高血圧症では持続的に強い圧力がかかり、血管の内皮が傷つき硬くなります。
どちらも最終的には動脈硬化を進めますが、“質の劣化”(脂質)と**“物理的ストレス”**(圧力)というアプローチが異なる点が大きな違いです。
共通点は“サイレントキラー”
自覚症状が乏しいまま進行し、心筋梗塞・脳卒中の引き金になる点で両者は「静かな殺し屋」と呼ばれます。
WHOが公開した心血管リスクチャートでも、コレステロールと血圧の双方を評価することで予測精度が高まると示されています。
“掛け合わせ”でリスクは倍増
国際レビューは「脂質異常症が高血圧を誘発し、高血圧が脂質の悪影響を加速する」という内皮機能障害の悪循環を報告しています。
AHAの研究では、高血圧+高LDLの人は高血圧のみの人よりも心筋梗塞・脳卒中リスクがさらに24%上昇しました。
メタボリックシンドロームの定義でも「内臓脂肪+(脂質異常・高血圧・高血糖のうち2項目)」とされ、両者の併存が強いリスク指標とされています。
検査と治療ターゲットの違い
|
項目 |
脂質異常症 |
高血圧症 |
|
主な検査 |
空腹時採血(脂質プロファイル) |
家庭血圧・診察室血圧測定 |
|
数値目標 |
LDL-C <120 mg/dL などリスク別ターゲット |
家庭血圧 <135/85 mmHgが目安 |
|
代表的薬物 |
スタチン、エゼチミブ、PCSK9阻害薬 |
ACE阻害薬、ARB、Ca拮抗薬、利尿薬 |
|
生活改善の核 |
飽和脂肪酸・トランス脂肪酸カット、適正体重維持 |
減塩(1日6 g未満推奨)、節酒、適正体重維持 |
生活習慣を見直す重要性について(コレステロール改善)
忙しい30代世代にとって「食事・運動・睡眠なんて分かっているけど続かない…」という声はつきものです。しかし、研究は“ほんの少しの積み重ね”でもコレステロール改善と動脈硬化予防に直結することを示しています。ここでは当院が患者さまにお勧めしている5つの柱をご紹介します。
食事の質を整える ― “何を減らすか”より“何を増やすか”
-
地中海食を1年間続けた高リスク者では、悪玉LDL粒子が酸化されにくくなり、粒子サイズも大きく変化して動脈硬化性が低下しました。
-
1日5 gずつ水溶性食物繊維を増やすと、LDLが平均 -5.6 mg/dL、総コレステロールが -6.1 mg/dL低下することが220群・14,505人のRCTメタ解析で確認されています。
-
日本人にも身近なオートミールはβ-グルカンが豊富。半カップ(約40 g)で2 gの水溶性繊維が摂れ、継続摂取でLDL低下が期待できます。
身体活動を“習慣化” ― 時間より頻度がカギ
-
WHOは「18~64歳は週150–300分の中強度有酸素運動」を推奨しています。
-
日本の『健康づくりのための身体活動ガイド(2023)』も、**週23METs時(目安:1日60分の速歩)**で生活習慣病リスクが3%低下すると報告しています。
-
148件のRCTをまとめた最新メタ解析では、有酸素+筋トレの複合運動が最も脂質改善効果が高く、LDL -7.2 mg/dL・HDL +2.1 mg/dLなど全指標を有意に改善しました。
体重を5%落とすだけでもOK
-
40人の無糖尿病肥満者を対象にしたCell Metabolism掲載RCTでは、体重わずか5%減で肝臓・脂肪・筋肉のインスリン感受性が著明に改善し、心血管リスクが低下しました。
-
18か月介入のWLM3P試験でも、5〜10%減量群はHDL上昇・TG/HDL比改善が顕著に認められています。
-
BMI25以上の方は「2〜3 kg減」を最初のゴールに設定しましょう。当院では無理のない減量プログラムを提案しています。
禁煙で“善玉”を増やす
-
喫煙をやめるとHDLが平均 +0.06 mmol/L(約+2.3 mg/dL)上昇することが45研究のメタ解析で示されています。
-
AHAの患者向けファクトシートでも「禁煙直後から心血管リスクは下がり始める」と強調されています。
睡眠とストレスを侮らない
-
12件・11万4,000人の前向き研究をまとめたレビューでは、子ども・若年層で**長時間睡眠(≧10 h)**がHDL低下とTG上昇に関連していました。
-
慢性的な睡眠不足や強いストレスは交感神経を刺激し、LDL産生を促進するとされます。当院では**「7時間睡眠+就寝前の深呼吸」**を推奨しています。
コレステロール管理は薬だけでは完結しません
- 食事:繊維・オリーブオイル・魚を増やす
- 運動:+10分の速歩×毎日
- 体重:‐5%でOK
- 禁煙:今日が一番若い“やめ時”
- 睡眠:質と量を確保
これらを同時に取り組むことで、相乗的にLDLを下げ、HDLを上げ、動脈硬化の進行を食い止められます。
「続けられるか不安…」という方は、ぜひ当院へお気軽にご相談ください。
30代でも間に合う生活習慣の見直し方法5選
30代をでも十分に脂質値は改善が期待できます。
ここでは医学に基づいた5つのアクションを、忙しい働き盛りでも今日から取り組める形でご紹介します。
“足し算”で食事を変える(水溶性食物繊維と地中海式の合わせ技)
- 〈水溶性食物繊維を1日+5 g〉アラビアガムやオートミール、もち麦などに多く含まれ、この量でLDLが平均5~6 mg/dL低下することが2023年のRCTメタ解析で示されています。
- 地中海食(魚・オリーブオイル・ナッツ中心)を続けたPREDIMED試験では、心血管イベントが約30%減少し、LDLも有意に低下しました。
- 朝食を「オートミール+果物」に、主菜を「青魚のグリル」に替えるだけでβ-グルカンとω-3脂肪酸を同時に確保できます。
週150分の“ながら運動”+筋トレ
- WHOは18~64歳に中強度有酸素運動150~300分/週を推奨し、心血管リスク低減を明記しています。
- 日本の『健康づくりのための身体活動ガイド2023』は**週23METs時(例:1日速歩60分)**で生活習慣病リスクが3%下がると報告。
- 有酸素+レジスタンスの複合トレーニングは、単独よりLDL-7.7 mg/dL・HDL+2 mg/dLと効果が高い最新メタ解析も示されています。
体重“-5%”が最強の近道
- セル・メタボリズム誌の介入試験では体重5%減で肝・筋・脂肪組織のインスリン抵抗性が改善し、LDLや中性脂肪も20~30%低下しました。
- 2〜3 kg減量でも腹囲が縮み、脂質プロファイルが有意に改善することから「見た目より中身」を目標にしましょう。
禁煙で“善玉コレステロール”を底上げ
- 日本人を含む解析で、禁煙後12週でHDLが平均+2.3 mg/dL上昇し、抗酸化能も改善したと報告されています。
- 喫煙はLDLの酸化を促進し動脈硬化を加速させるため、「本数半減→医師と禁煙補助薬」の段階的アプローチでも確実なメリットがあります。
睡眠“6~8時間”の確保とストレス軽減へ
- 成人2,500人超の前向き研究で、睡眠6時間未満はHDL低下・中性脂肪上昇が有意に多発しました。
- 深呼吸や軽いストレッチを取り入れた就寝前のルーティンが自律神経を整え、LDL産生を抑えるとの報告もあります。
不安な方は当院へご相談ください
脂質異常症は “数値でしか気づけないサイレントキラー” です。
厚生労働省 e-ヘルスネットでも、放置すると脳梗塞や心筋梗塞など重大な動脈硬化性疾患を招く危険性がはっきり指摘されています。
健康診断でコレステロールや中性脂肪が基準を外れた方、あるいは家族歴・生活習慣が気になる方は、早めの受診をおすすめしています。
西にっぽり内科消化器クリニックが選ばれる5つの理由
西日暮里駅徒歩すぐの好立地
通勤途中やお買い物ついでに立ち寄れるアクセス。雨の日でも負担が少なく継続通院しやすい環境です。
女性専門医によるやさしい内視鏡検査
胃・大腸カメラは鎮静下で実施。検査が苦手な方でも安心して受けられるとご好評です。
生活習慣病を熟知した総合的な診療体制
胃腸・肝胆膵だけでなく、脂質異常症・高血圧・糖尿病など内科全般をワンストップで管理。
土曜午後・日曜午前の診療枠を拡大
「平日は時間が取れない」という働き盛り世代でも無理なく通院を継続できます。
Web予約・オンライン診療に対応
スマホから24時間予約OK。血液検査結果のオンライン説明や生活指導も実施し、通院の手間を最小限に抑えます。
「ちょっと相談してみたいな」「もう少し詳しい説明を聞きたい」というお気持ちになられたら、どうぞ遠慮なく当院へお問い合わせください。
お電話などから、検査や予約に関するご質問をお受けしています。
もちろん、事前のカウンセリングだけでも構いません。スタッフ一同、皆さまの健康を最優先に考え、誠心誠意サポートさせていただきます。
「当クリニックのご予約はLINE予約がおすすめです!」